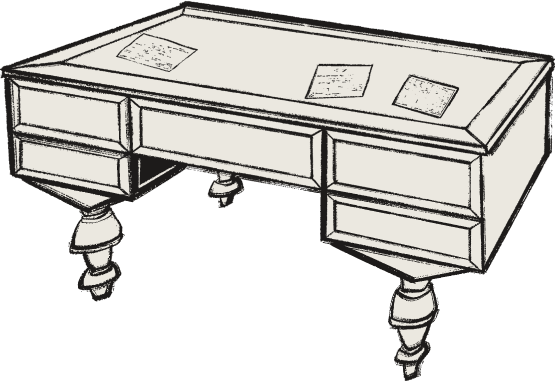


いいえ
メイドがグッジェに寄り添ってクスクス笑っていると、ドアを叩く音と叫び声が聞こえてきた。
「お待ちください!」と叫んで、メイドは庭の窓を慎重に開け、小太りのグッジェをその隙間から外に押し出した。そしてちょっと考えてから、ヒステリックにシャーッというネコをつかんで、同じように窓から外に出したんだ。 「ここはまだ日本の領土です。あなたがたが入る権利はりません!」と彼女はドアを開けて兵士たちに行った。「それから、犬をきちんとつかまえていてください。ネコが怯えて庭をウロウロしますから!」とほとんど泣きそうになりながら言う。それから、「私は何もしりません。上流階級のブルジョアジーに虐げられた労働者階級の哀れなメイドですもの!」と、ロシアの洗濯おばさんから最近聞かされたことを繰り返した。危機一髪!この言葉が、メイドに殴りかかろうとしていた民兵の動きを止めたんだ。鎖につながれたワンワン吠える犬をつれて、兵士は急いで空っぽの部屋を調べた。そいつは悪態をつきながら唾を床に吐いて、ドアをばたんと閉めた。そうしてようやく去って行ったんだ。



窓から庭に追い出されちゃうなんて、もうぼくはぷんぷんだよ! だけどメイドは優しい声で家に戻ってきなさい言ってくれた。ボールにクリームを入れ、イワシの箱まで開けてくれたんだよ。クリーム!久しぶりのごちそうだ!だからぼくはメイドを許してあげることにしたんだ。
それから数日、ぼくはメイドが空っぽの部屋を掃除するのを手伝った。うしろをついて回って、みゃあみゃあ言ってあげた。 夏が秋にかわろうとしている。 メイドはぼくを古いバスケットのカゴにいれた。前に、杉原一家と旅行に言った時に使ったバスケットだ。それをスカーフで覆って、小さな荷物を肩に担ぐ。そうして駅へむかった。メイドは駅で、ベルリンへ向かう杉原一家に別れを告げ、自分のお兄ちゃんを待つことになっている。お兄ちゃんはカウナスまで迎えにきて、メイドを村まで連れて帰ってくれることになっているんだ。昔、メイドが都会に幸せを探しに行く時に、出て行った村に




駅では人だかりができていた。みんな急いで、押し合い、スーツケースをひっぱっている。僕たちはベルリンへ向かう電車のホームを見つけた。だけど、駅の中でも千畝はビザを求める人々に囲まれていた。メイドはため息をついて、ベンチに腰掛けた。ベンチには、つみあげた枕の山みたいにどっしりとした女の人が座っていた。彼女はすぐにぐちぐちと文句を言い始めた。「なんて駅なのかしら、秩序もなにもあったもんじゃないわ。馬市場のジプシーみたいにみんな乱暴に押し合うし、私のハンドバックもとられそうになるし、切符売り場じゃ、干し草の袋を取り合うポーランド人みたいにやりあってるわ。私はチケットを買うためにやつらを肘で押しのけなくちゃいけなかったのよ」話しかけられたけれど、メイドは黙っていた。すると、太った女の人はまた話しかけてきた。「みてごらんなさいよ。この愚か者たちが電車に殺到している様子を。まるで天国にむかうドイツ人みたいに割り込んじゃって。それにこの人たち、みて、ポーランド系ユダヤ人よ。まるで・・・まるで市場のユダヤ人のように騒いでるじゃないの。食肉用の動物みたいに誰かに殺されるとでも思ってるのかしら、無駄に騒いじゃって!」これにはメイドも怒った。その女性に向き直ってこう言ったんだ。「あなた、恥ずかしくないの?この人たちがあなたに何したって言うのよ?ある日突然、あなたも疫病神にとりつかれて八方塞がりになってみればいいのよ。その時にあなたが泣くかどうか見ものでしょうね!」
太った女は鼻を鳴らし、髪の根元まで赤くなった。ぼくはバスケットの隙間からそれを見ていた。彼女は立ち上がって、メイドのそばに唾を吐いてヒステリックに叫んだ。「ふん!ユダヤ人お抱えメイドのくせに!」その女は、駅の食堂に向かってよろめきながら歩いていった
その同じ食堂から、パン屑だらけの口髭を拭きながら、メイドのお兄ちゃんが人ごみをかき分けてやってきた。メイドのおずおずとした挨拶には答えないで、彼女の服がつまった袋を持ち、怒ったようにバスケットをちらりと見た。そしてうなずいた。「行くぞ。馬車はむこうだ。先は長いぞ」
次の章へ