華麗なるスパイたち
ラジオさんのこと
ニーサンはテルシェ・イェシーバの生徒だ。そしてテルシェもしくはテルシェイは、リトアニアの街だ。リトアニア人が言うには、ニーサンはダッチマン。つまりオランダ人の子孫だってさ。テルシェには500人のユダヤ人の生徒がいる。ヨーロッパからだけじゃない。北アフリカや南アフリカからも来ている。だけどそれは別に大事なことじゃない。大事なことはサッカーさ。ニーサンは熱心なサッカーファンなんだ。いつもリーグ表を作って、結果を書き込んでいる。サッカーのことを誰かに話したいし、アヤックス・アムステルダム(オランダのサッカーチーム)への情熱を叫びたい。だけど、一体リトアニアに何人のオランダ人がいるっているんだよ?せいぜい4人か5人。まぁ、どこを探したらいいかわかっているのなら、みつけられるさ。
リトアニアにいる最高のオランダ人といえば? それはラジオさんだ。彼はもちろんPSVアイントホーフェン(これもオランダのサッカーチーム)のファン。フィリップスで設立されたこのチームは、地元フィリップス代表の心に最も近い存在なんだ。だけどラジオさんは遠く離れたカウナスにいる。しかもめちゃくちゃ忙しい。このラジオさんの本名はヤン・ズヴァルテンディクっていうんだ。


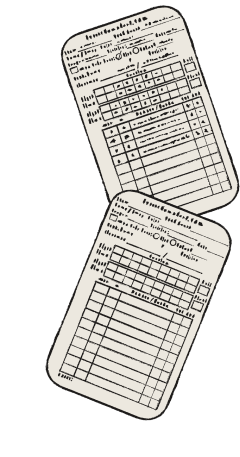
ズヴァルテンディクはニーサンにオランダの新聞や、それ以外にもサッカーのスーパーリーグのカードの切り抜きなどを、よく送ってきてくれた。だけど、そのうちラジオさんはサッカーについてあんまり語らなくなって、新しいガジェットのことを話すようになったんだ。世界初の電気カミソリ、フィリシェーブのことをさ。石鹸や水を使わずに、おそらく鏡すらも使わずに、ひげや口ひげを剃ることができるんだって!
だけどニーサンはカミソリには興味がなかった。サッカーに興味があるのだもの。ここのところ、そんなニーサンの後ろを新入生のアーロンがついてまわっている。まるで迷子の子猫のように彼が行くところどこにでもついてゆくんだ。「学生食堂はどこにあるの?」「インクはどこで買えるのさ?」「あと何日か、部屋に泊まらせてくれないかな?」ってね アーロンと両親は、リトアニアに着いたばかりだった。ソ連から逃げてきたユダヤ人避難民と共に、彼らはポーランドから来ていた。今はもう存在していないポーランドから。

アーロンの家族は、今はヴィリニュスに滞在していだ。アーロンはニーサンに家族からの手紙を読んで聞かせた。学校に通い始めたばかりの小さな弟トリク、他のユダヤ人難民の少女たちと一緒に工芸学校で裁縫を学んでいる妹リア、彼らが行くのを免れたウッチのゲットーのこと、ひどり仕打ちをするソ連やナチスのこと......
「この世界に僕たちの場所はあるのかな」とアーロンは問いかけた。「963人のドイツ系ユダヤ人が乗ったハンブルク発のサン・ルイ号のことを知っているかい? その船はキューバにもアメリカにも受け入れてもらえなくて、アントワープに停泊するまでの1ヶ月以上、幽霊船のように行ったり来たりしてたんだよ。船の乗客は、また別のどこかに逃げなくちゃいけないのにさ。でも結局どこにも行き場所はないだろ?」


ニーサンは、テルシェ・イェシーバの先生たちみたいにアーロンを教え諭そうとした。苦しみは無駄ではないのだ、苦しみは心の世界とこの地上を一つにする助けとなる、苦しみは神との関係をより高い次元へと導くのだと。あの日までは。 ある日のこと。テルシェ・イェシーバの先生たちが急に別れを告げ、ヴィリニュス、モスクワ、 ウラジオストク、そして日本を経由してアメリカに行ってしまったんだ。テルシェ・イェシーバが開校し続けられるよう、アメリカのユダヤ人たちに資金集めを頼むために。ニーサンはものすごく腹が立った。ニーサンだってアメリカに行きたいのだから。ニーサンの家族は、昨年オランダからアメリカに渡っていて、ニーサンだけがリトアニアに残って勉強している。リトアニアは静かで安全だから。だけど、以前は安全だったこの場所が、今は使い古された椅子のようにだらりとして、ひびが入りそうだ。アーロンだけが、毎晩もう存在しないポーランドを思って泣いていた、これまでは。でもこの頃はニーサンも一緒になって泣いている、ナチスに占領されたオランダを思って。

あと一ヶ月もすれば、と震えるアーロンが手紙を見せてきた。ヴィリニュスではユダヤ系の知識人が次々と逮捕され、新聞社やユダヤ人学校が閉鎖されるだろうという知らせだった。アーロンの家族はせっかくポーランドでナチスから逃れたというのに、今はソ連の赤軍が洪水のようにリトアニアに押し寄せてきている。 季節は春から夏に移り変わろうとしていた。 公園で出会った医者のジエンコーヴィッチスは、以前ラジオさんからX線装置を買ったことがあるそうだ。その彼が言った。ラジオさんはもうラジオを売っていないのだ。オランダはドイツに占領されてしまい、もうあそこから特別な機器を受け取ることができなくなったからねと。「だからズヴァルテンディクさんのことを、ラジオさんと呼ぶのはおやめ」と医者はニーサンに言った。「彼は今や、領事館の領事さんなのだからね」

それを聞いたニーサンは急いで家に帰って、シャツと靴下と歯磨き粉をかばんにつめて、古くからの友達、ハイムの住む寮のドアをノックした。二人の親友はカウナスへ、ラジオさんがいるオランダ領事館へと向かうことにしたんだ。哀れな瞳をもったアーロンも、その後をついていった。だってカウナスとヴィリニュスは遠くないし、アーロンは家族がこれからどうなるか心配でたまらないのだから。
そして今、二人の友、ニーサンとハイムはオランダ領事館の前で領事を説得しようとしていた。元ラジオセールスマンであるこの臨時の領事を。ナチスドイツの手がまだ届いていない、オランダ領、カリブ海のキュラソー島へのビザを発給してくれるように頼んでいるんだ。領事はこう言った。キュラソー島にはビザは必要ない。しかし私は決められない、島の総督自身が、島に入る許可を与えるかどうかを決めるのだ。(そして総督が誰かを「許可する」と言ったのをまだ聞いたことがないのだ。)


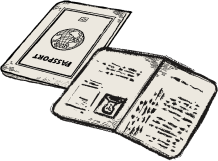
だからこそですよ、とニーサンは領事に頼んだ。うまいことやってくれませんか。パスポートに最初の一文だけを書く。
「カウナスのオランダ領事館は、キュラソー島とスリナム島に入るのにビザは必要ないことを認めます」 そして、つ目の文章は省略する。「入国には島の総督の許可が必要です」